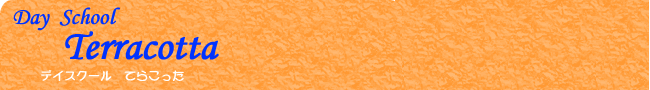|
大悪魔が、父親とその三人の息子、軍人のセミョーン、商人の太鼓腹のタラス、畑を耕している馬鹿のイワン、そして、口のきけない妹とが、仲良く暮らしているのが気に食わなくて、彼らに大喧嘩をさせ、めちゃくちゃにしてやりたくなった。ちび悪魔たちに命じた。セミョーンの係りの悪魔は、セミョーンに勇気を吹き込み、戦争を仕掛けさせ、負けさせる。タラスの係りの悪魔は、タラスに妬みの心を起こさせ、何を見ても買いたくなるようにさせて、借金漬けにする。イワンの係りの悪魔は、イワンの腹を痛くさせ、土を固くして、畑を耕すことが出来ないようにする。
「トルストイの民話だが、今の人間たちも、こんな三種類になるのではないか。戦争をしたいやつ、金持ちになりたいやつ、せっせと黙々と汗水垂らして働くやつ、だいたい、そんなものだな。」
英太は、箱根の宿で、夕食の後、また、酒を飲みながら、もはや、還暦前後の元柔道部の仲間と話している。
「だけど、戦争をしたい人間はいないだろう。一応、みんな、平和を願っているのではないのか。」
セミョーンの悪魔の作戦は上手く行って、セミョーンは、戦いに負けて、領地を取り上げられ、戻ってきた。イワンは快く、セミョーンを迎え入れた。ちび悪魔の度重なる妨害にも、くじけることなくせっせと畑を耕していたイワンは、ちび悪魔から、藁から兵隊を作り出す方法を教わっても、その兵隊たちに楽器を演奏させ、歌を歌わせて喜ぶばかりだった。セミョーンは、イワンに兵隊をたくさん作らせ、また、戦争に行ってしまった。セミョーンは、国を攻め取っていったのだが、足りないから兵隊をもっと作れ、とイワンに言った。しかし、イワンは、戦争で人が死んだから、もう、兵隊は作らないと言う。
「今でも、戦争をしたがっている人間はいるようだな。それに対抗するつもりで、ますます、軍隊を互いに増強しようとしている。結局、戦争が起こらなくても、無駄な出費だ。」
「だけど、そうして、軍隊がにらみ合って、平和が、一応は続いているのではないか。」
セミョーンは、更に兵隊を作って、逆らうものたちを押さえつけて、セミョーンを恐れさせ、必要なものは、すべて兵隊たちを使って、自分のものにしていった。セミョーンを失脚させたい悪魔は、隣の国を手に入れるために、ますます強い軍隊を作ることをそそのかし、セミョーンは、そのようにした。しかし、一度は上手く行ったが、インドの王が、セミョーンに真似て、更に強力な軍隊を作り、攻め込んできたセミョーンの軍隊をやっつけてしまい、セミョーンは、命からがら逃げ出した。
大悪魔は、イワンをそそのかし、軍隊を作らせようとしたが、イワンは軍楽隊がいいと言い、大悪魔は自分で、イワンの国の人々に、ウオッカと赤い帽子が貰えるから兵隊になれと言っても、イワンの国の馬鹿者たちは、酒も帽子も自分たちで作れるからと言って、笑うばかり。遂に、兵隊にならないと死刑にするからと命じても、兵隊になっても殺されると言って、イワンに談判して、イワンがみんなを死刑に出来る訳がないと言って、みんな、兵隊にならなかった。
とうとう、隣国のゴキブリ王が、大悪魔にけしかけられて、イワンの国を攻めてきた。イワンの国の人々は、誰も抵抗しない。むしろ、ゴキブリ国の兵隊たちに、何もかも渡して、そんなに苦しいなら、一緒に暮らそうと勧める。ゴキブリ王が、家や穀物を焼き払い、家畜をすべて殺すように命じるが、イワンの国の馬鹿者たちは、泣いているばかりで、好きなだけ持っていけと言う。ゴキブリ国の兵隊たちは、嫌になってしまって、逃げていった。
「戦争が起これば人が死ぬ。戦争が起こらなければ、無用の長物。そんな軍隊が何故必要なんだい。災害救助隊で、充分だ。」
地を裂きて 地を潤して 葱の生ふ
2011年 11月22日 崎谷英文
|